英語
教科書を正しく活用しましょう。
様々な文法の例文を載せているすばらしい教材です。
広島県の公立高校における2025年度入試の英語の平均点は、21.4点となりました。2024年度は24.1点、2023年度は24.0点であったことを踏まえると、昨年度は過年度と比べると難しかったと言えるでしょう。しかしながら、出題された問題を見ると決して難しい問題ばかりではありませんでした。2026年度入試も一筋縄ではいかないものになることが考えられます。
2022年度入試より一部出題形式に変化がありましたが、その後も同様の出題形式が見られました。2026年度入試においてもその流れを踏襲すると考えられるため、どのように対策すればよいのか、綿密に作戦を立てておきましょう。
では、細かな出題形式について触れていきます。まずリスニング問題に関してですが、2021年度以前にもあった択一問題と英作文に加えて、2022年度より対話の補充問題が追加されています。一文、あるいは一言で答えればよい比較的シンプルな問題であり、複数の解答パターンが考えられます。2024年度では週末にしたことを、2025年度では放課後の予定を題材にした対話となっており、シチュエーションの想像がしやすい身近な題材選びが今後も続いていくと言えそうです。
続いて大問2に関して。対話文とそれに伴う資料の読解問題である、という点は変わっていませんが、2022年度以前まで出題されていた英作文問題が削除されています。また、近年においては、2022年度を含めて出題され続けていた「空欄に1語補う」形式の問題が記号問題に置き換わっています。これにより、近年における大問2は全問が記号問題という形となっています。しかしながら、本文での会話の内容を表や文章でまとめる問題が追加されており、内容の理解がより重要になってきています。題材に関しては、2024年度は留学生との古着の処分方法の話し合い、2023年度は一日の野菜の摂取量についての話し合いを扱っていました。一日の野菜の摂取量などリスニング問題と同様に、こちらも身近な題材選びが続いていくと思われます。
そして大問3。こちらは出題形式の変化は無いと言っていいでしょう。但し、大問3には本文をしっかりと読み解いたうえで英作文をさせる問題がありますから、難易度の高いものである、という認識はしっかり持っておきましょう。
最後に大問4。ここの変化が最も大きいのではないでしょうか。2021年度までの対話の空欄補充に加えて、2022年度より新たに「二者択一し、その理由を記述する」という形式の英作文問題が追加されました。この出題形式は2025年度にも引き継がれ、題材は外国語映画を見るときには、吹き替えの映画と字幕付きの映画はどちらがよりよいかを選ぶもの、となっています。どちらの立場をとっても構いませんが、2024年度・2025年度では、理由を2つ挙げる必要がありました。自分の書きやすい方をしっかりと見極めましょう。
出題形式の変化については以上となります。総じて求められている能力は、「主に日常生活において、自分の意見を英語で伝えることができる」というものになっていますね。こういった英作文問題においては、「自分の伝えたいことを、自分の扱える文法や単語で書く方法はないか?」ということを脳内で検索する力、これが最も重要であると言えます。そんなことができたら苦労しないよ、という声も聞こえてきそうですが、様々な文法の例文を載せているすばらしい教材を皆さんは持っているはずです。そう、教科書です。教科書には「身近なシチュエーションで」「自分の考えを説明する」対話が山のように載っていますよね。これは広島県の公立高校入試の英語に対しての夢のような教材ですので、教科書をひたすら音読してみてください。一度だけではなく何度もです。繰り返し声に出すことによって、英文が頭・目・耳に馴染んできます。すると、どういうシチュエーションでどういう英文を使っているのかが分かってくると思います。教科書って実はすごいヤツなんです。もちろん英語が書けなければ何も始まらないので、問題集の例文等、簡単な日本語を英語に直して書いてみる、といった記述の練習もしてみるといいでしょう。
本番まであと少し。普段の勉強に加えて英語を書く練習をしつつ、隙間時間で積極的に教科書の音読に努めてみてください。
数学
まだまだ時間はあります。
過去問を解いて苦手な単元を無くしていきましょう。
近年、数学の平均点は少しずつ上がって、易しくなっているのではと思われますが、難易度の変化はあまりないと感じています。難しい問題より、確実に得点できるところを落とさないようにしていきましょう。大問ごとの出題予想とその対策についてお伝えします。
大問1では、計算問題と簡単な知識を問う問題が出題されます。計算問題は、正負の四則、連立方程式、ルートの計算、2次方程式です。解の公式は必ず覚えておきましょう。知識を問う問題では、1次関数の傾きと切片を求める問題、球の表面積・体積、錯角・同位角が出題されると予想します。1次関数の式の形、球の表面積・体積の公式を見直しておきましょう。
大問2では、連立方程式の文章題が出題されると予想します。割合と速さの問題を復習しておきましょう。解く過程を記述するかもしれません。何をx、yとするのか、連立方程式は正しく作れているか、単位は合っているのか、xとyを求めたのち最終的な解答は何になるか。これらを意識しながら解く練習をしましょう。
大問3,4では、年によって違いますが、関数の問題と証明問題がよく出題されます。今年度の関数問題では、放物線と直線が交わる問題が出題されると予想します。放物線と直線の交点を求める、その交点と原点とでできる三角形の面積を求める、その三角形の面積を2等分する直線を求める、これらはよくセットで問われるので、練習しておきましょう。
証明問題は、相似の証明が出題されると予想します。必ず図形に等しい所、平行な所などを記入し、証明の道筋を予想してから書き始めましょう。定義は仮定になりますが、定理は仮定になりません。何が定義で、何が定理なのか、覚えにくいです。そういう時は、必ず図形の説明をしましょう。平行四辺形なので、~=~。正三角形なので、~=~。このように書けば減点されません。
大問5,6では、日常生活に関連した文章問題がよく出題されます。文章量が多く、会話文や資料もあります。丁寧に読み込んでいけば、1問目は簡単に求められたりするので、頑張って読み込みましょう。
以上が出題予想と対策についてです。
計算の途中式は、大きく丁寧に。途中式を書けば、整理しながら進められ、計算ミス・符号ミスを減らせます。計算ミスが多い方は、途中式を丁寧に書くことから始めましょう。
公立高校入試までまだまだ時間はあります。過去問を解いて苦手な単元を無くしていきましょう。
理科
前日まで学力を上げやすいので、
最後まで粘ってみましょう。
理科は4分野(生物・地学・物理・化学)から、それぞれ出題されます。理科は前日まで学力を上げやすい科目です。合格ラインぎりぎりだと思われる生徒は最後まで粘ってみましょう。逆転合格を目指す生徒は開き直って山を張ってみましょうか。
生物分野だと植物に注目しましょう。植物の分類・光合成や蒸散(中1)、進化や遺伝(中3)などです。 地学分野は天体の年周運動(中3)、地震と火成岩、地層と堆積岩(中1)などです。
物理分野は光の進み方、凸レンズの働き(中1)、オームの法則(中2)などです。
化学分野では化合と分解(中2)、イオン化傾向(中3)などは出題可能性が高いように思われます。
県立高校の過去出題問題の中で上記出題可能性の高い分野に近い範囲のものは必ず解けるようにしておいてください。これらを身に付けられれば理科を武器に入試を突破できるはずです。期待しています。残り時間も少なくなって来ました、頑張ってください!
社会
やればやるだけ得点に直結!
逆転のチャンスを含んだ教科。
社会は、やればやるだけ得点に直結する科目です。「苦手だなぁ」と思っている生徒は特に伸びますから、最後の最後まで諦めず努力しましょう。
さて、5教科の中で得点分布のばらつきが大きいのがこの教科の特徴です。言い換えると、逆転のチャンスを多分に含んだ教科であると言えます。出題の特徴としては、「資料から考察し、その結果を表現させるもの」が多いということです。ですから、記述を求める設問に対し、しっかり答えられるかどうかが合否のポイントとなります。それでは設問ごとに解説していきます。
大問1は地理的分野です。基礎的な知識として、*世界地図の中での赤道の位置や日本列島と同緯度の国や地方。*日本と同じ東経135度が通る国々。*時差の計算。*気候による世界各地の生活の違いや風習。これらは必ず押さえておくべきです。しばらく出題されていない石炭・石油・鉄鉱石などの地下資源についても同様です。
大問2は歴史的分野です。今年は形式としては年表が出題されます。一昨年は文化史、昨年は経済についての事柄が出題されましたから、今年は政治史が出題されるのではと注目しています。どちらにしろ飛鳥から昭和まで幅広く出題されますので、年表を傍らに置きながら、一問一答式の問題集などで確認しておくと良いでしょう。
大問3は公民的分野です。基本的な知識として、日本国憲法については充分把握しておく必要がありますから、すっきりとまとめられた参考書などを利用して知識を整理しておいてください。また、地方自治に関する問題はここ数年出題されていませんから、要注意です。国と地方の財政や為替相場と国際収支なども教科書を利用して確認しておきましょう。
大問4は総合問題です。例年、環境や少子高齢化など社会問題についての出題です。国際関係なども出題されます。基礎的な知識としては国際連合の仕組みや仕事について確認しておく必要があります。また、温暖化現象などはエネルギー問題とも絡めて記述にも耐えられる知識が必要です。
合否のポイントになるであろう記述問題は、解答を仕上げるのに時間がかかりますから、後回しにしてもいいでしょう。あせる必要はありません。時間はたっぷりありますので、落ち着いて最後に記述問題に取り組みましょう。問題文や資料をしっかり読み取り、題意をはずさないようにきちんと書くことが大切です。作文を書く要領で校正をすることも忘れてはいけません。問題文を一字一句読み切る根性と丁寧さが勝敗を分けます。与えられた制限時間を残さず使い、悔いを残さぬように持てる力を存分に発揮してください。
最後になりましたが、これから入試までの日々を有意義に過ごし、合格を勝ち取られることを祈っています。
国語
本番では時間配分を
考えながら進めることが大切
国語は大問1「物語文」、大問2は「説明文」、大問3は「古文漢文」という構成になっています。
細かい話から始めますと、漢字の書き取りの出題は小学生の時に習った漢字ばかりです。漢字の苦手な生徒は小学生範囲の漢字を見直すと良いでしょう。
古文では「現代仮名遣い」に書き換える問題は必ず出題されています。ここは絶対に点を取れる問題ですので外さないように学習しておきましょう。
大問1「物語文」では落ち着いて物語を楽しむつもりで読み込んでください。しっかり読んだ方が早く解答を見つけることができます。記述の問題で解答としてまとまらない場合は、ひとまず後回しにして先に進みましょう。国語は時間がかかる科目ですから、時間配分を考えながら進めることが大切です。
大問2「説明文」では、素直に作者のロジックに沿って読まなければ解答が正解から離れてしまいます。くれぐれも作者のロジックと自分の主張を戦わせながら読まないように気を付けてください。
大問3「古文漢文」では読みづらい古い言葉が並ぶので苦手意識を持つ生徒も多いと思いますが、たくさんの注釈が付いていますので、それを利用すれば内容を読み取れます。また問いの中からもヒントを拾うことができます。問題文が短いので大問3は短時間で仕上げたいと思います。時間が余ったら、減点されないように記述の解答を見直してください。
本番まで2ヶ月を切りました!
体調に気をつけて本来の力を発揮できるよう備えましょう!
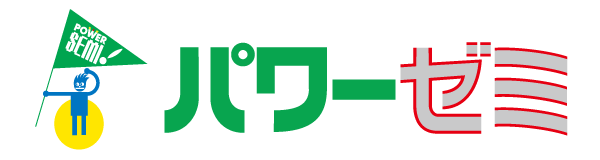

 >>>詳しくはコチラ
>>>詳しくはコチラ